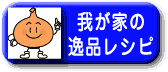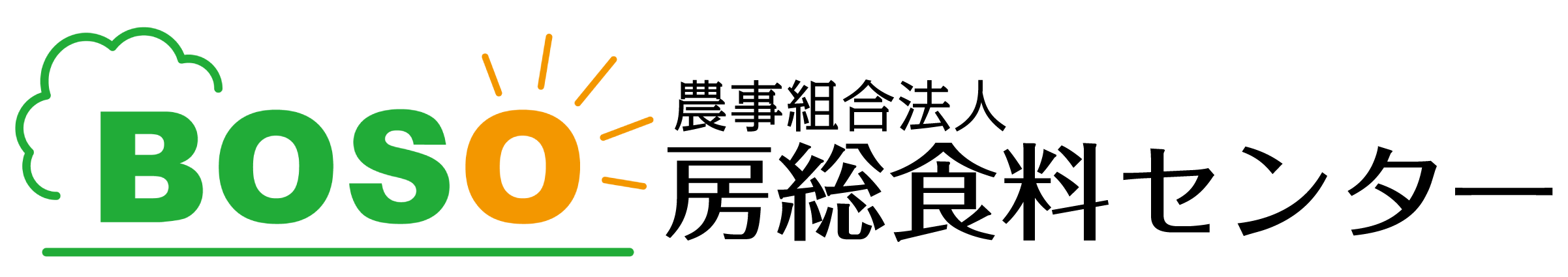生い立ち
今夏に掲載予定の「トマト」で詳しく触れたいと思いますが、トマトは、ナス科の野菜に数えられ、南米アンデス山脈が原産。15世紀末にはコロンブスによってヨーロッパへ、日本へは江戸時代に伝わります。
ミニトマトの歴史は浅く、大正時代にはチェリートマトと呼ばれる、ホオズキくらいの大きさをした小型トマトが作られましたがあまり食用されず、食用ミニトマトとして急速に普及したのは、まだ最近といえる昭和時代末期のことです。
ちょっと言わせて!

畑のミニトマトは、まるでブドウのように、房状に実がなっています。
しかし、ブドウとちがい、いっせいに実が赤るむわけではないので、収穫するには、畝1列ごとに何周もまわりながら、赤らんだ玉から順に1玉ずつ丁寧に、丹念にもいで行くのです。意外にも労力を要する野菜です。
そんななか、ミニトマトのビニールハウスの中を自由に飛び回る昆虫がいます。「マルハナバチ」です。

ただ飼っているだけではありません。ミニトマトの花の蜜を交配する役割を担い、糖度の食味向上や、防菌にも大きく役立っています。
健康マル得メモ
こちらも「トマト」でお話ししますが、真っ赤な色は、「リコピン」という色素から来ているもので、ビタミンAに効力はないものの、ベータカロチンが少量ながら含まれ、ガン予防に効果をもたらすようです。
「知っ徳」 調理裏技メモ
へたをつまんで、ひとくちで食べるのが主流といえましょう。お弁当のおかずと一緒に入れたり、生野菜のサラダの彩りに添えたりするのも、皆さんおなじみですね。
しかし料理の飾りにも活用してみるのも、これぞ知られざるかくれた「料理裏ワザ」でしょう。